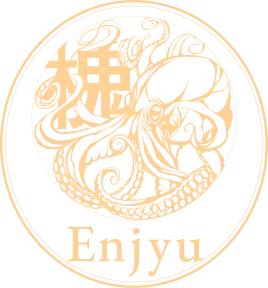葉の色が変化するのはなぜ?
こんにちは。
レジンテーブル槐です。
お盆も終わり、紅葉の季節が近づいて来ました。
紅葉する木の代表的なものとして、カエデ、イチョウ、ヤマウルシ、ツツジ類などがありますが、
これらは全て広葉樹です。
またその中でも、落葉広葉樹という分類に区分され、
秋になると葉が全部落ちてしまい、冬を越して、春に新しい葉をつけるという特徴があります。
では、葉がなぜ赤や黄色に変化するのでしょうか。仕組みはこうです。
秋になり日照時間が減ると光合成をする時間が短くなります。
そうすると、春夏に増加したクロロフィル(光合成をおこなう緑色の色素)は不要になって、分解されていきます。
もともと葉の中に存在するカロテノイド(黄色い色素)は、クロロフィルの減少によって台頭するようになります。
これがいわゆる「黄葉」の状態です。
その後、少しでも太陽光を吸収するために、葉に残っていた糖分からアントシアニン(赤い色素)がつくられます。
このアントシアニンが増えれば葉は赤く、黄色い色素が多い場合は黄色く見えます。
両方が上手く混ざり合うと、オレンジ色に変化します。
これが紅葉のメカニズムです。

夏は暑く、日照が多く、適度な降水があると秋に美しい紅葉になりやすいとされています。
しかし、暑ければ暑いほどいい、日照時間は長ければ長いほどいい、降水量は多ければ多いほど良いかというと、一概にそうとは言えないようです。
夏が猛暑の年は例年、紅葉のシーズンは遅れる傾向にあるので、
今年もそのような予想がされていますが、秋の風物詩である紅葉を今年も楽しめるといいですね。