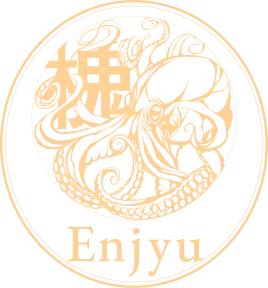木目はどうしてできるの?
こんにちは。
レジンテーブル槐です。
木でできている商品を購入するとき、木目を気にしたことがありますか?
おそらく、色や形だけでなく、木目の出方を基準に木材家具選びをしたという方も多いことでしょう。
ほかの素材にはない、木材らしさを感じさせる要素の一つが「木目」です。
全く同じ模様は二つと存在しないため、木目は木材の個性を表現する要素の一つとなっています。
では、この「木目」とはどのようにして出来るのでしょうか。
木目が出来る主な理由は、木の「年輪」と「道管」の存在、そして「樹木の生育環境と剪定の仕方」と言われています。
年輪とは木の断面にできる同心円状の輪のことを言います。
1年に1つずつでき、それが重なっていきます。
なので、樹齢はその年輪を数えることによって分かります。言わば、木の成長の軌跡と言っていいでしょう。

道管は、根から吸収した水や養分を全体に運ぶための管状の組織のことです。
ルーペで見ないと見えないくらい小さい穴がそれです。
この道管の配列によって木目の出方が異なってきます。
樹木の生育環境とは、そのまま木が育つ環境のことで、ストレスの多い環境か否かや日光の当たり方、気候の差などで木目に違いが出ます。
また、剪定によっても木目の出方は異なります。
木を横にして、縦方向に輪切りにしていけば(丸太)↑の写真のように、木目は丸くなります。
横方向に切れば、一般的に木目は左右を繋ぐような形で出現します。同心円状の丸が出現することはほぼありません。

これらの要素が複雑に絡み合い、出現するのが「木目」です。
今度木材の家具や工芸を見たら、これらの要素に注目しながら見てみると面白いかもしれません。
木目(もくめ)と杢目(もくめ)の違い
木材屋さんや家具屋さんの記事を読むと、「杢目」という言葉が良く出てきます。
これも木目と同様に「もくめ」と読みますが、少し異なる意味をもちます。
「木目」は木の年輪が作り出す模様全般を指し、その中でも気象や生育環境の影響で現れる幻想的で複雑な模様を「杢目」と呼びます。
木材の切り出し方の違いによって異なった現れ方をする木目を板目や柾目(まさめ)と呼びますが、
杢目はこれらとは一線を画す個性的で美しい木目です。
全ての木材に見られるわけではないので、希少価値が高いというのも特徴です。

折角なら「杢目」のある、個性的な自分だけのお気に入りのものを探してみて下さい。
槐ではテーブルのオーダーメイド制作も承っております。
お好きな木目をもつ無垢材で、あなたなだけのオリジナルなテーブルを作ってみませんか。