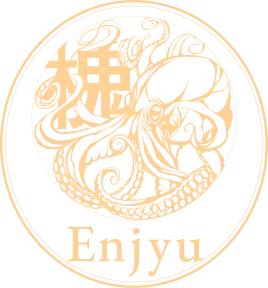テーブルの歴史を知ろう
こんにちは。
レジンテーブル槐です。
現在、皆さんが使用しているテーブルは様々な形や素材で出来ていることでしょう。
では、それらテーブルの始まりは一体いつ、どこで生まれたのでしょうか。
世界のテーブルの歴史
石を用いたテーブルなど、原始的な家具の面影は人類が登場した時代から散見されますが、
我々が思い描く「本格的な家具」が登場するのは4000~6000年前とされています。
家具の発展には、農耕文化と木工技術の定着が関係します。
狩猟文化から農耕文化への変化が「定住」の概念を人類に持ち込み、
それに伴い固定式のテーブル、椅子、棚などの家具が重宝されるようになっていきました。
約5000年前に登場したとされるエジプト文明は、木製家具の当時の最先端であったとされます。
砂漠地帯であるエジプトは木材の乾燥に適しており、
この頃すでにベッド、棚、テーブル、椅子といった我々が普段目にする木製家具の原型のようなものを発明していたというのです。
中世になると、大型化し甲板と脚が分離できる架脚式の構造になり、
また、小さな丸テーブルと書見台を組合わせたようなライティング・テーブルが普及しました 。
その時代からは、今ではよく見るような猫脚のようなものだったり、
テーブルが大型化したりと豪華な作りに変化していきました。
ルネサンスの時代になると、上流貴族の邸館に食事専用の甲板と脚と貫が固定されたダイニングルームが置かれるようになりました。
17世紀の後期ごろからは、生活様式の多様化と住宅内に多くの部屋が設置されるにつれて、
テーブルの種類も増加しサイドテーブル、ドレッシングテーブルなどが現れます。
18世紀にはフランスの上流階級の間でコーヒーが流行し、専用のコーヒーテーブルが生まれました。
19世紀末になると、テーブルは装飾的なものから機能性を重視する傾向が出はじめ、現代へと続いていきます。
日本のテーブルの歴史
日本においては、古墳時代~飛鳥時代に活躍した聖徳太子(574~622)が、
机を使っている絵が残っていることから、机はかなり昔から存在したことが分かっています。

しかし、ことダイニングテーブルに限っては、登場したのはまだ最近です。
もともと日本人は、木の床や畳に直接座る床座式と呼ばれる生活様式で暮らしていたので、
世界で比べるとその普及が遅かったようです。
食事の際には、畳や木の床に直接お皿を置き、そこに食事を並べていました。
江戸時代であっても、畳や縁台に座ってせいぜい折敷(おしき、四角いお盆状の膳)の上に食事を載せて食べるくらいだったようです。
ダイニングという概念が生まれたのは、明治時代といわれており、その時に登場したのがちゃぶ台でした。
ちゃぶ台は床に座って使う、短い四本の足がついた木製の食卓のことです。
昔のアニメ(ちびまる子ちゃんやサザエさんなど)でよく見るので、想像しやすいでしょう。
昭和初期ごろに一般家庭にも普及し、広く使用されるようになりました。
このちゃぶ台がダイニングテーブルへと切り替わったのが昭和戦前期頃。
広く普及したのは第二次世界大戦後です。
戦後焼け野原となった日本においては、住む場所がなくなり、政府主導の公営住宅が多く建設されるようになりました。
それらコンクリート住宅は戦前に比べ十分な広さがなく、コンパクトな暮らしを強いられるようになります。
そのため、台所と居間を一緒にする必要がありました。
そこで目を付けたのがダイニングテーブル。この頃から一気に一般家庭に普及していったのです。
日本のダイニングテーブルの登場には、少し哀しい歴史が背景にあるのですね。
しかし、悪いことばかりではありません。
ダイニングテーブルが登場する以前の日本では、家族が集まって食事を摂るという習慣がありませんでした。
また、黙食がルールで、修行のような役割を持つこともあったそうです。
食事は、それに集中し、味や香りを深く味わい、食材への感謝の気持ちを表すという、
ある種神聖な行為であるという認識が広く普及していました。
この考えが、ダイニングテーブルの普及に伴い変化したのです。
ダイニングテーブルでの食事は家族が集まって会話を楽しむ、コミュニケーションの時間となり、
家族観の変化にも影響を与えました。
まとめ
私たちが生活するうえで欠かせないテーブルは、様々な歴史を経て今日もコミュニケーションの場を生み出しています。
もっとあなたらしく、会話が弾むようなテーブルを。空間が華やぐようなテーブルを。
私たち槐(エンジュ)のレジンテーブルを見に、お気軽に展示場までお越しください。